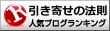「すぐに緊張してしまう」と悩んでいる人は多いです。
人前でスピーチするときなど、緊張することがあると思います。
一般的に人間はリラックス状態のほうがパフォーマンスが良いと言われており、緊張状態にあると、自分の実力以下の結果しか出せなくなってしまう傾向があります。
緊張そのものは人間の持つ本能的な反応ですから、悪いものではありませんが、できれば緊張しないでいたいものです。
今日のトピックは緊張しないための対策と対処法になります。
緊張するとはどういう状態のことなのか?
「緊張している」とはどういう状態なのかということを簡単に説明すると、「コンフォートゾーンの外側にいる」ということになります。
コンフォートゾーンというワードはこのブログにも何度も登場していますが、初めて見る方のために簡単に解説したいと思います。
コンフォートゾーンとは「自分が心地よいと思う環境」のことです。
例えば普段サラリーマンをしている人が、世界的な大企業の社長が集まる会合に何かのきっかけで同席することになったら、すごく居心地が悪いですよね。
その居心地の悪い状態が「コンフォートゾーンの外側にいる」ということです。
人前でスピーチをしたことがない人にとって、その体験はとても居心地が悪いものになることは想像に難くないと思います。
しかしその「コンフォートゾーンの外側」も、回数をこなすうちに慣れてきます。
その環境に慣れてくると、その居心地の悪かった環境が新しいコンフォートゾーンになります。
「人前でスピーチをする」ということが当たり前になったら、緊張しなくなりますよね。
テレビに初めて出演するときは緊張するでしょうが、毎日のようにテレビに出ていればやがて緊張することもなくなります。
つまりその「環境に慣れる=コンフォートゾーンを広げる」ことができれば緊張しなくなるわけです。
緊張しないための対策
緊張しないための対策は「その環境に慣れる」ということです。
そのためにできる事前の対策はイメージトレーニングです。
実際にその環境で練習できるのであれば、イメージトレーニングである必要はありませんが、大抵の場合本番と同じ環境を自分で再現するのは難しいのでイメージトレーニングという手法を取ります。
脳は現実と非現実を区別できないという習性がありましたね。
梅干しを口の中に入れている姿を想像したとき、口の中に唾液が広がる感覚があると思います。
それは脳が現実とイメージを区別できていないから、梅干しが口の中にあると勘違いして唾液を出す命令をしているからです。
本番さながらに自分が人前でスピーチしている姿を想像し、イメージトレーニングをします。
状況はできるだけ具体的にイメージしたほうがより効果的です。
何度もイメージをする(脳がそれを現実だと認識する)と、その環境に慣れてきます。
そうすると本番のときに緊張することは少なくなります。
緊張しないための思考法
緊張しないようにするために必要な思考法もあります。
この章では緊張しないための思考法について書いていきたいと思います。
背伸びをしない
人が緊張する一番の理由はこれです。
背伸びをするというのはどういうことか簡単に説明すると、「自分のことを良く見られたい」と思うことです。
要するに人の目が気になるから緊張しているわけです。
ではどうすればいいか考えてみましょう。
そのためにはその人前でスピーチをすることの本当の目的が理解できていないことを自覚する必要があります。
あなたが人前で話すのは、聞き手に何か大切なことを伝えたいからであって、あなたがよく見られるためにスピーチをしているわけではないはずです。
であれば自分のスピーチに磨きをかけ、「いかに聴衆の心を動かすか」ということに意識を向けるべきです。
人の目が気になるから緊張するというのは、スピーチではなく自分自身に意識がフォーカスしているから生まれる感覚です。
自分のことを気にしている時点で、そのスピーチに全力投球していないということです。なぜなら本気で取り組んでいたら、自分のことを考えている余裕などないからです。
緊張しない(したくない)と考えない
そもそも緊張するというのは、人間の本能的な反応であり決して悪いものではありません。
緊張せずに無謀なことばかりをしていると、簡単に命を落としてしまうことになります。だから防衛本能として、そのような反応が身に備わっているのです。
緊張している人によくありがちな思考が、「緊張してはいけない」と考えてしまうことです。
しかし、実はこれは逆効果なんです。
潜在意識の特徴を覚えているでしょうか?
このブログのかなり初期の記事になるので、文章の質が低くて恐縮ですが、この記事の中に潜在意識の特徴が解説されています。
その中の一つに「潜在意識は肯定形・否定形を区別できない」というものがあります。
つまり「緊張したくない」ことは「緊張したい」ことであると認識されてしまうということです。
そもそも「緊張したくない」と考えている時点で、意識が「緊張」に向いてしまっています。
それは自ら緊張したいと言っているようなものです。
さきほどお伝えした通り、緊張そのものは悪いものではありません。
そしてこのような本能的な反応は潜在意識の働きによるものです。
ですから、その緊張している状況をしっかりと味わってみるのもいいと思います。
どっぷりとその環境に浸っていると、「なぜ自分はこんなに緊張しているのだろう」と冷静になる瞬間がやってきます。
そして、潜在意識に感謝しましょう。「自分を失敗から守るために、緊張させてくれたのだ」ということが理解できると、緊張させてくれた潜在意識に感謝できるようになります。
相手を知る
僕もよく経験があるのですが、まったく見ず知らずの相手に電話をするときなどはとても緊張した記憶があります。
「相手が細かいことにうるさい人だったらどうしよう」とか思うと、きっちりとした言葉遣いができないと叱責されるのではないか、という恐怖が根底にあったのだと思います。
でも相手はひょっとしたらめちゃくちゃフレンドリーな人かもしれないわけです。
ただ相手のことを知らないから一方的に悪い方に考えて緊張しているだけです。
だからもし事前に相手のことを知ることができるのであれば、その情報を入手しておくことが緊張を和らげることにもつながります。
失敗を恐れない
「失敗すると恥をかく」という恐怖があるから、緊張してしまうのです。
でも例えばスピーチを失敗しても、別に命を取られるわけではありません。
考えようによっては「その失敗があったおかげで、スピーチが怖くなくなった」と解釈することもできます。
もしそう考えることができたら、むしろその失敗は大きなプラスになるわけです。
ただその失敗が大きなトラウマになってしまうこともあるので、常にプラスに解釈できる癖はつけておく必要はありますが。
失敗するのが怖くなくなると緊張する回数も減ります。
例えばゴミ箱に紙屑を投げ入れるのに緊張する人はいないと思います。
しかし、もし失敗したら全財産を失うと言われたら、おそらく多くの人は緊張するはずです。
それは行為そのものが緊張の原因になっているわけではなく、その行為に対する自分の解釈が変わったから緊張するようになったということを意味しています。
「失敗しても命を取られる訳じゃない」ぐらいに軽く考えると、緊張もやわらぐはずです。
今日は以上です。
最後まで読んでいただきありがとうございます。